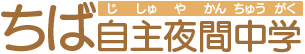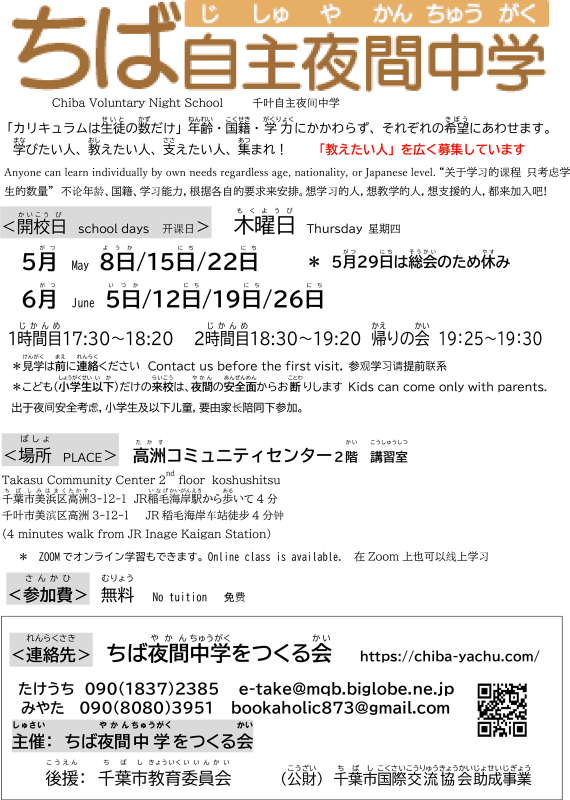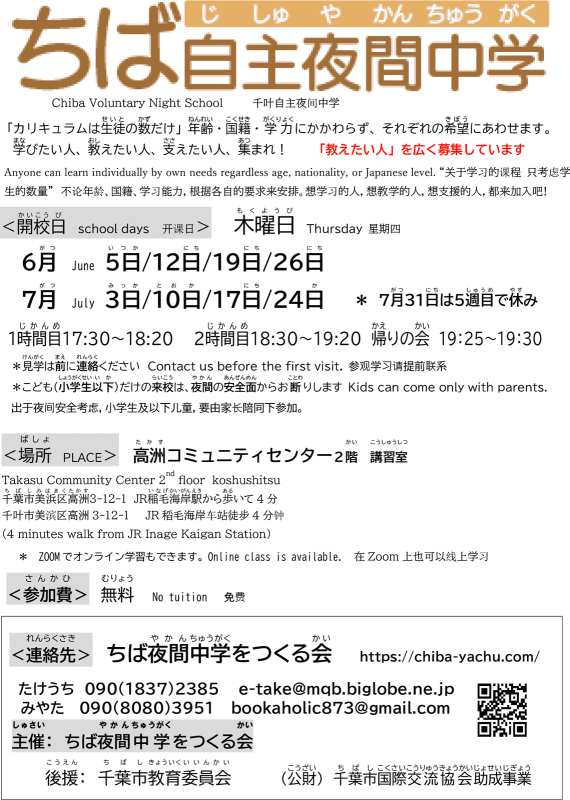【🎥映画(えいが)の紹介(しょうかい)】「35年目(ねんめ)のラブレター(らぶれたー)」その2
35年目のラブレター公式サイト
千葉市のイオンモール幕張新都心でみてきました。感想です。
◇
「もし今の記憶を持ったまま過去に戻れるとしたら、いつの時代に戻るだろうか?」
そんなことを考えたことのある人は、案外多いのではないだろうか。たとえ今幸せな人でも、人生の中で何かを遣り残したという思いがある人はいると思う。この映画「35年目のラブレター」の主人公、西畑保さんの「奥さんにラブレターを書く」という目標は、彼の人生で最も大きな「遣り残したこと」というにちがいない。読み書きができないことで虐げられ、職にあぶれ、命の危機を経験してきた西畑さんが、世を呪うこともなく素晴しき生涯を送っていく証、それがアメリカ映画のようなどんぞこから一発逆転、世界を救うヒーローになるといった現実味のないものではないこころのこもった「ラブレター」なのだろう。このようなこころの支えがある人は、本当の意味で強い。
この映画の様々な登場人物の中で西畑さん夫婦とともに大きな存在になるのが、夜間中学の谷山先生である。先生は、どっかのドラマのように名言を連発するわけではなく、「贈る言葉」も「青葉城恋唄」も歌わない。この谷山先生は元々中学教師だったのだが、担当していたクラスが学級崩壊してしまい、追われるように夜間中学に転任してきた。先生も挫折を経ていたのである。そのような背景も手伝ってか、先生は生徒たちにイチから向き合う。たとえば西畑さんは漢字はもちろん、ひらがなも書けなかった。本当にイチからのスタートだった。話はそれるが、私が十代のころ常々思っていたのは「先生って冷たいな」ということだった。今だったら「パワハラ」「虐待」と言われて大問題になっていたであろう先生もたくさんいたし、いじめや不登校の子に本気で向き合っている先生など皆無と言ってよかった。特に高校の先生は「高校は義務教育じゃないんだから嫌なら退学しろ」といった調子で、私は「こんな奴らに税金から給料が払われてるなんて、税金払うの馬鹿らしいな」と思っていた(私学の先生はどうかは知らないが、まあ、大差ないだろう)。私の脱税願望(?)は置いといて、夜間中学の先生は私がたくさん見てきた「お役人」教師には決して務まらないだろうな、としみじみ感じた。もちろん生徒にも様々な事情を持った人が登場する。個人的に印象に残ったのは、しょうた君という少年だ。彼は人の視線が恐くて学校に行くことができなかった。初登場時は視線をさけるためパーテーションの中で息をひそめて授業をうけている。私自身、背後からの笑いごえ(特に若い女性の)に恐怖感を覚える症状を持っているので、しょうた君の気持ちは多少なりとも理解できる。そんな彼に西畑さんは少しずつ近づいていく。好きなアイドルの話をしているとクラスメイトのかつて不登校で形式上卒業した少女が話へ加わり、彼らは少しずつうちとけていく(もっとも西畑さんはそのアイドルを全くしらないようだったが)。そして彼らは西畑さんの卒業式にOBとして出席する。大きくクローズアップされるわけではないのだが。もうパーテーションに隠れる必要のなくなったしょうた君をはじめとしたかつての西畑さんの学友たち、家族、先に定年となり「卒業」した谷山先生、彼らの清々しい表情はかつて暗闇にいたことを乗り越えて、今はそれぞれの素晴しき道を歩んでいる証であろう。もちろん、私が今更言うまでもなく、西畑さん夫婦の絆を感じさせてくれるシーンの数々を見のがしてはならない。すべて挙げていたら話が終わらないので一つだけ語らせていただくと、ラストシーンの少し前、西畑さんの書いたラブレターを若かりしころと齢を経た夫婦が交互に読み合うシーン。もしかしたらあのシーンは西畑さんの叶わなかった夢だったのかもしれない。それでも、西畑さんの手紙はきっと届いているということは、なぜだか信じられる。
さて冒頭にて「過去に戻れるとしたら・・・」という話をしたが、結論から言うと過去に戻ることはできないし、辛い過去を消すこともできない、その事実にこころが折れ、人生を投げてしまう人もたくさんいる。夜間中学は西畑さんのような人、外国籍の人、不登校だった人、私のように学校に行ってはいたけど退屈だった人など色々な人がいる。この人たちをあえて総称するなら「過去に負けなかった人たち」というのはどうだろう。私は個人的に「過去は変えられないから大事なのは今と未来」といった「そんな風に考えられるなら苦労しないよ」と思うポジティブ発言は好きではないが、夜間中学に通うことが、辛い過去を上回るものを得られることであることを自主夜中の末席に連なっている私も願ってやまない。この映画は、観た人の背中を「めげたらアカン」と強く叩いてくれることだろう。(了)
(古澤)