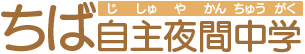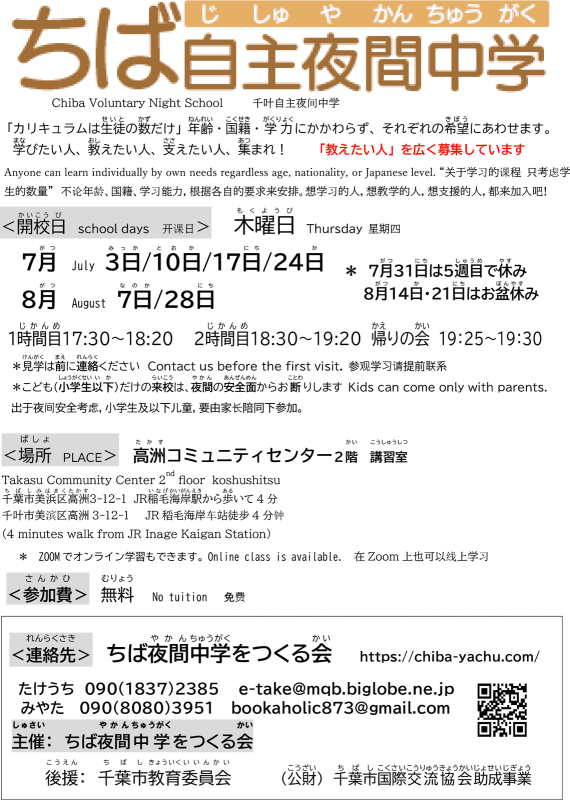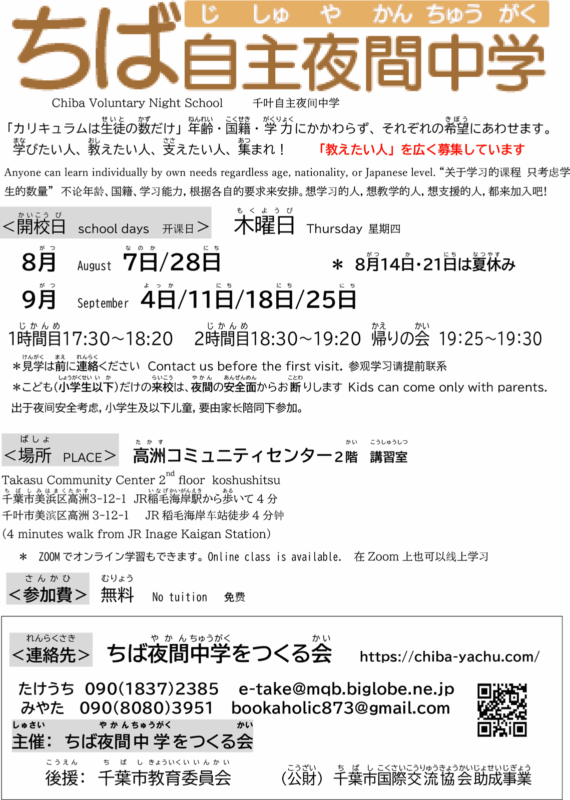【📚本の紹介(ほんの しょうかい)】「俺(おれ)の夜間中学(やかんちゅうがく) 何(なん)のために学(まな)ぶのか―港湾労働者(こうわんろうどうしゃ)飯野正春(いいのまさはる)の半生(はんせい)」
「俺の夜間中学―何のために学ぶのか―港湾労働者飯野正春の半生」(盛 善吉/編 連合出版)
「俺の夜間中学」を読んで
作者の盛 善吉氏(2000年逝去)は、シナリオライター・作家・人形劇団主宰・映画監督と多彩な顔をもつ。「俺の夜間中学」は1983年5月に発刊、大阪天王寺夜間学級が舞台。
貧しさのために小学校も満足に通えず、形式中学卒業の同和地区出身の飯野正春の半生記でノンフィクション。前半は、生まれ故郷の鹿児島で15歳でデカン(デッチ)~17歳でハッダと船乗り(魚の行商)~運搬船のカシキ(雑用兼賄)~20歳、大阪に出て仲仕(港湾労働者)をしながら全港湾の組合活動をしているところまで。後半は、奈良から35歳で天王寺夜間学級に越境入学し、仕事と学業を両立していく様子が描かれている。前半が識字前、後半が識字後と読替えても良い。識字前も識字後もヒアリングがよくされて生き生きとした飯野正春の気持ちと行動がわかる。特に、識字後の彼の行動が凄まじい。夜間中学全体としての修学旅行での校長への直談判(修学旅行に参加できないものが過半数いるのはおかしい→与えられた前提を疑う、新しいルール創造、変化即応)のエピソードは秀逸、次の夜間中学の人たちのためにも物申していく姿は、飯野正春の真骨頂と思う。識字後に、職場で学校で仲間のためにエネルギッシュに動いていく彼の姿を通して、家庭・親・学校・教師、学ぶことは何のためから学校教育の在り方を深く考えさせられる。彼の言葉の変遷(鹿児島弁~大阪弁~奈良弁)も、折々の生活感が汲み取れ面白い。
夜間学級での彼の仲間の詩……金持ちがなんだ、身分がなんだ、貧乏がなんだ、そんなものは台風でふっとんでしまえ、これも強烈なインパクト…。飯野正春は、その後も定時制高校へ進学し学びを続ける。生きていれば、私と同年齢、自立し、変わらず学び続けていることと思う。
作者の盛 善吉氏は、反骨の人。映画でも、同和地区・原爆・国内外国人差別等重いテーマを撮られている。夜間学級に関しては、奈良の私設夜間学級の「うどん学校」がある。これもはやく視たいものである。
(吉井 薫)
何のために学ぶのか
飯野正春さん
港湾労働者であった1976年、35歳で大阪の天王寺夜間中学に入学する。3年生の時に近畿夜間中学校生徒会連合会の会長、職場では、全港湾の安全衛生委員を務める。当時は昼間の中学校に行く3人の子の父親でもあった。ご存命なら84歳。お会いしたい方です。
サブタイトルにある通り、ここには飯野さんの夜間中学との出会い、そこで獲得した「人間は何のために学ぶのか」が実に実にストレートに書かれている。著者の盛善吉さんは奈良自主夜間中学校の記録映画「うどん学校」の映画監督。映像作家の文章はいきいきとして、夜間中学の仲間たち、70年代後半の夜間中学を巡る動きを描きだしている。主人公も作家も「まっすぐ」で、圧倒されてしまった。「学ぶ」とは何か、「文字を獲得する」とはどういうことか、皆で考えるためにお勧めします。
飯野さんは被差別部落に生まれ、貧しさ故中学はほとんど行かず、15歳で奉公に出される。やがて港湾労働者となり、搾取に対抗するために全日本港湾労働組合に入る。そこで、「誰か、字習うて来い」と言われ、籤に当たって(!)天王寺夜間中学に行く。
この豪快でまっすぐな男が「一番初め行った日はね、怖くてな。行きたいのが半分、行きたくないのが半分なわけや。(中略)どうしよう、どうしようと思うて学校のあたりをぐるぐる三回くらい回ったな」と言うのがなんだかおかしい。まさに人生を変えた籤だったわけだ。
その時は、自分の名前とひらがなが書けるくらいだった。夜間中学で文字を持たない人々と出会い、「教育を受ける権利」に目覚め「人間らしい生活をする権利」を実現するために動き回る姿が痛快だ。憲法、労働三法を学び、職場では、労働者の団結のために力を尽くくし、夜間中学では、全員が修学旅行に行けるよう、就学援助金が受けられるようにと校長に談判する。学びは人間らしく生きるための武器であった。
当時の天王寺夜中には400人ほどの生徒がいた。病気で学校に行けなかった人、被差別部落出身で小さい時から働かないと一家が食べていけなかった人、朝鮮のオモニ・アボジ、中国やブラジルの引揚者、沖縄出身者、戦争に巻込まれて学校に行けなかった人。
この本は、夜間中学関係者のメールで見て気になり、探したところ千葉市の図書館の閉架書庫に1冊だけあった。奥付に1983年5月とある。2か所ほど綴じがはがれそうで、壊さないようにそっと開いて読んだ。手元に置いておきたい本だが、古本のサイトを見ても見つからない。あとがきには、夜間中学生・オモニのために活字を大きくし、ルビをふった出版社への感謝が述べられている。その心遣いに、本を作った方々の心意気をも感じる。今、多くの人に読んでほしい本です。再版を望みます。
(宮田 敬子 花見川区)
※この文章は「市民の千葉をつくる会」が毎月出しているニュース「市民の千葉をつくる会」No.182(2025年5月1日)に寄稿したものです。「市民の千葉をつくる会」にお断りして掲載します。(宮田敬子)